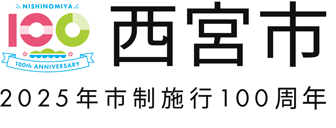成年後見制度のご案内
更新日:2026年1月16日
ページ番号:91876420
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害、発達障害などの理由で判断能力が不十分な人は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な人を保護し、財産管理や身上保護などの支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度においては、ご本人の判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」の3種類
法定後見制度 | 任意後見制度 (判断能力が不十分になる前に) | |||
|---|---|---|---|---|
| 後見 | 保佐 | 補助 | ||
| 対象者 (利用者本人) | 判断能力が欠けているのが通常の状態の人 | 判断能力が著しく不十分な人 | 判断能力が不十分な人 | 判断能力がある人 |
| 支援する人 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 | 任意後見人 |
| 代理することができる行為(注1) | 原則としてすべての法律行為 | 民法13条1項記載の行為のほか、 申立てにより裁判所が定める行為 | 申立てにより裁判所が定める行為(注2) | 本人との契約で定めた行為 |
| 同意権 取消権(注3) | 原則としてすべての法律行為 | 法律上定められた重要な行為 | 本人の同意を得たうえで、 家庭裁判所が定めた法律行為 | なし |
(注1) 一部の行為については、家庭裁判所の許可が必要となります。
(注2) 民法13条1項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。
(注3) 成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。
(参考リンク)
成年後見制度・成年後見登記制度Q&A(法務省)(外部サイト)![]()
後見ポータルサイト(裁判所)(外部サイト)![]()
法定後見制度
本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度です。
利用の仕方
1.本人の住所地にある家庭裁判所に後見等の開始の審判を申立て
【申立てのできる人】
本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長(身寄りのない高齢者の場合など)、検察官など
(主な四親等内の親族)
・親、祖父母、子、孫、ひ孫 ・兄弟姉妹、甥、姪
・おじ、おば、いとこ ・配偶者の親、子、兄弟姉妹
2.家庭裁判所
申立書の提出を受けて、審理が開始されます。裁判所から事情を尋ねられることや本人の判断能力について鑑定が行われることがあります。
審判とともに本人の法律上又は生活上の事情に応じて、家庭裁判所が成年後見人等に最も適切と思われる人を選任します(申立人の希望どおりの人が選任されるとは限りません)。
3.成年後見人等が支援を開始
成年後見人等は、一般的に1年に1回、後見等事務の状況の報告を家庭裁判所から求められ、適切に事務が行われているか確認されます。
成年後見人等に対する報酬は、事務内容等などを総合的に考慮したうえで、家庭裁判所が適正妥当な金額を審判します。
※手続きの詳細については、申立てする家庭裁判所にご確認ください。
(参考)成年後見制度(後見・保佐・補助)(神戸家庭裁判所)(外部サイト)![]()
任意後見制度
任意後見制度は、ご本人に十分な判断能力があるうちに、将来認知症などで判断能力が十分でなくなったときに備えて、あらかじめ自分自身で選んだ人(任意後見人受任者)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
その後、本人の判断能力が十分でなくなった場合に、本人や任意後見受任者等からの申立てで家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。このときから、任意後見受任者は正式に任意後見人となり、任意後見契約の効力が生じます。
利用の仕方
1.本人と任意後見受任者で任意後見の内容を検討
2.公証役場で、公正証書にて任意後見契約を締結
任意後見契約が締結されると、公証人の嘱託により、契約内容が指定法務局(東京法務局)で登記されます。
3.本人の判断能力が十分でなくなったとき、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立て
【任意後見監督人選任の申立てのできる人】
本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者
4.家庭裁判所で任意後見監督人を選任し、任意後見監督人の下で任意後見人が契約内容に従って本人の支援を開始
本人の親族等ではなく、第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士等の専門職や法律、福祉に関わる法人など)が選ばれることが多くなっているようです。
※手続きの詳細については、公証役場や申立てする家庭裁判所にご確認ください。
(参考)全国の公証役場(日本公証人連合会)(外部サイト)![]()
(参考)成年後見制度(後見・保佐・補助)(神戸家庭裁判所)(外部サイト)![]()
相談窓口
身よりがないなどで申立ができない場合
・西宮市役所 くらし支援課又は障害福祉課![]()
高齢者の相談窓口
・お住まいの地域の地域包括支援センター![]()
障害のある方の相談窓口
・お住まいの地域の基幹相談支援センター![]()
専門的な相談窓口
・西宮市高齢者・障害者権利擁護支援センター![]()
<成年後見人などの候補者の紹介、申立ての相談>
・高齢者・障害者総合支援センター「たんぽぽ」(兵庫県弁護士会)(外部サイト)![]()
・公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート兵庫支部(司法書士による成年後見人等)(外部サイト)![]()
・権利擁護センターぱあとなあ兵庫(兵庫県社会福祉士会)
神戸市中央区坂口通2-1-1 兵庫県福祉センター5階
電話:078-222-8107/ファックス:078-265-1340
お問い合わせ先
くらし支援課